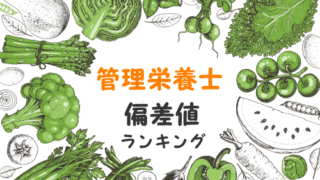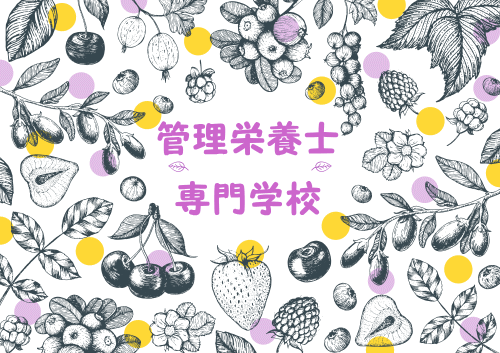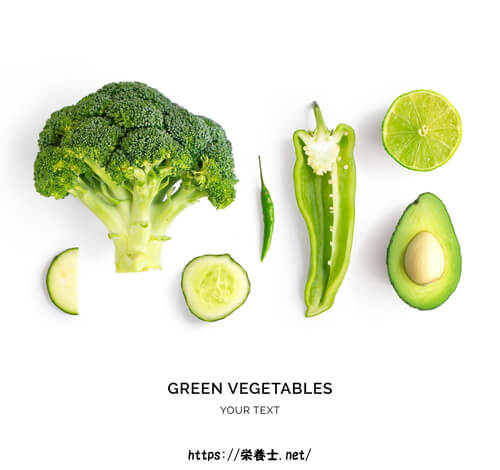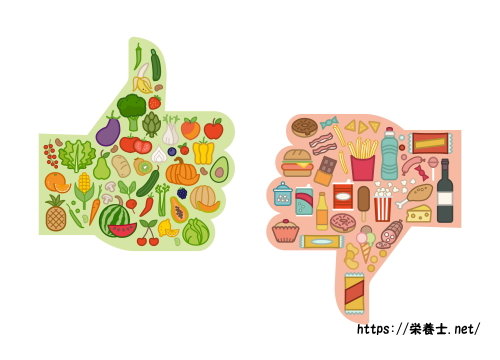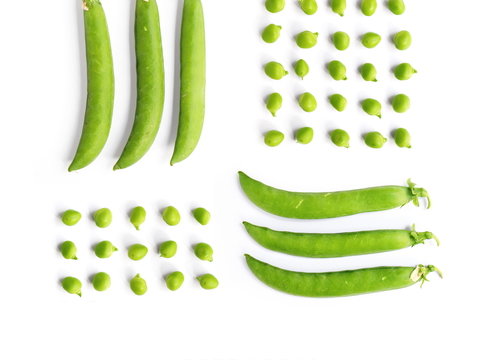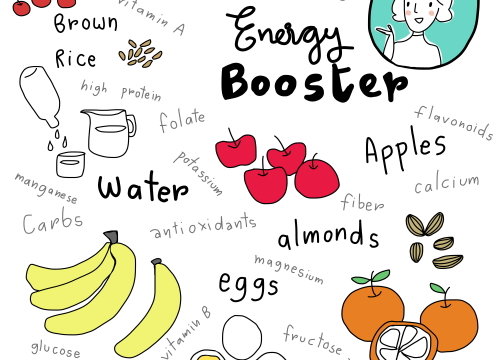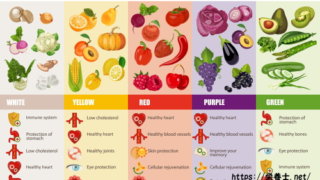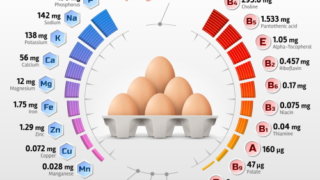32歳の女性です。管理栄養士養成の4年制大学を卒業し、卒業した年の3月にに試験を受け5月に資格を取得しました。
試験への挑戦はその時の1回のみです。
参考になるかわかりませんが、私の勉強方法を公開します。
管理栄養士を目指した理由
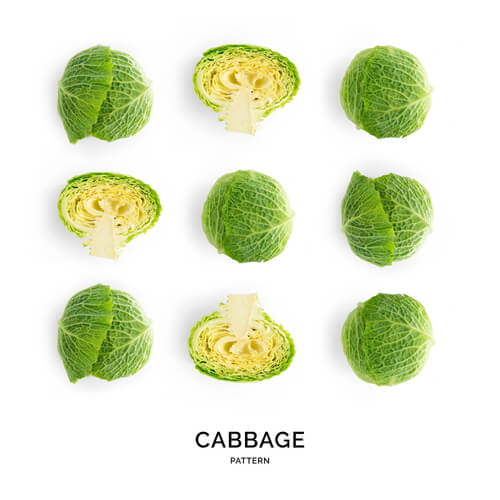
私が出た大学はほぼ全員が管理栄養士の試験を受ける為、正直資格への挑戦はごく当たり前のような感覚はありました。
ただ、どうしても病院で働いて栄養指導がしたかったので、絶対に合格したいという気持ちは強かったです。
だからと言って入学当初から病院で働きたかった訳ではなく、きっかけは病院での実習です。
栄養指導を見学して、患者さんが笑顔になり患者さんから感謝される仕事であることを感じ、病院で働くことを強く希望するようになりました。
管理栄養士試験の勉強
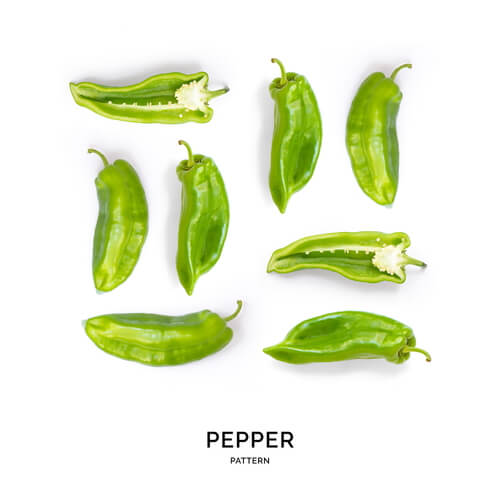
本格的に試験へと向けた勉強を始めたのは授業自体が国家試験対策をし始めた4年生からだったと思います。
私の大学での国家試験対策のスタイルは、用意された試験を受けて〇点以下の人達は授業を受け、それ以外の人達は自習というものでした。
その試験が3~4回程度あったように記憶しています。正直言って、2~3回は成績が悪く、授業を受けていました。
授業の内容は過去問を解いていき、先生が解説をしていくというスタイルです。
午前中のみの日もありましたが、夕方までみっちりあった日もあったかと思います。
授業以外でも勉強方法にも記載します。
参考書

参考書は大学で指定されていたこともあり、「クエスチョンバンク」を使用していました。これは正直かなりおすすめです。
解りやすいことはもちろん、イラストが多く見やすいです。
どの参考書もそうだと思いますが、情報が完璧に記載されてはいません。
参考書に載っていなかった情報は全て参考書に書き込み、参考書を見れば全てが網羅出来るようにしていました。
この参考書を最初から最後まで4回くらいはやったと思います。
1回目は正直わからない事ばかりでしたが、とにかく理解をしようという気持ちでやりました。
時間が掛かってもじっくり理解するまでは先に進まない気持ちで取り組みました。
最初は苦しいですが、2回目、3回目と繰り返しやっていくと、3回目あたりで科目ごとの繋がりが面白いようにわかってきます。
⇒スポーツ栄養士の就活・仕事内容・待遇。スポーツジム勤務の体験談
暗記が重要
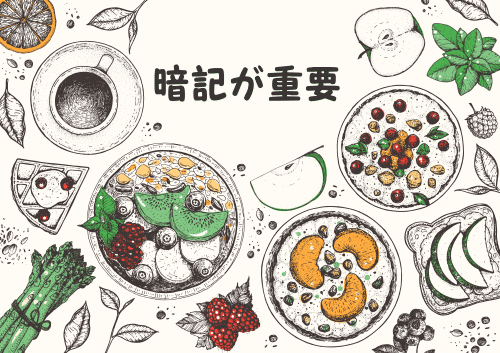
私は凄くそれを実感しました。試験内容には理解するだけの内容だけでなく、覚えることも多々あります。
なかなか覚えられないものに関しては自分の部屋やトイレ等に貼り、目に触れる機会を多くしました。
この際、視るだけでなく声にも出して耳からも情報を定着させるようにしていました。
また、わからないことはその日中、もしくは翌日には解決するように心がけていました。
基本的に大学で勉強
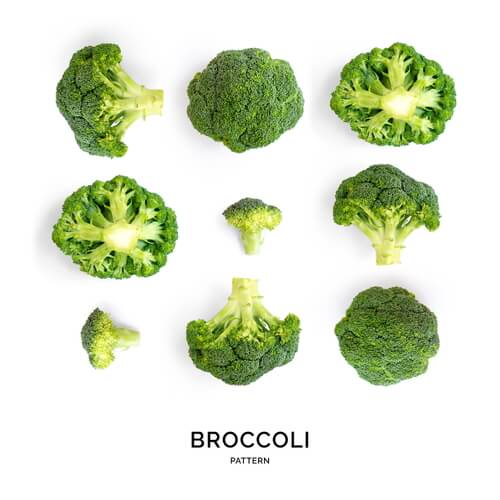
私は自宅で勉強するよりも大学で勉強をする方がはかどるし、わからないことはすぐに聞けるので基本的には大学で勉強をしていました。
特に私が心掛けていたのはわからないことは最初から先生に聞くのではなく、まずは友達に聞くということです。
なぜかというと、自分がわからなかったことを友達がわかっていた場合は、理解度の遅れを認識することが出来るからです。
友達もわからなかった場合は、一緒に先生に聞きに行くようにしていました。
そうすることにより、友達も自分に聞いてくれるようになり、説明出来なければ本当に理解していなかったということにも気づくことが出来ます。
友達を巻き込むことによって知識が記憶に残りやすいと感じています。
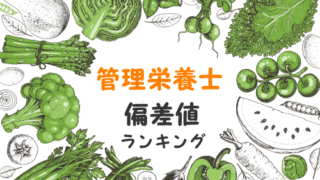
やる気が起きない日は

しかし、毎日毎日やる気に満ち溢れている訳ではありません。気が進まない日もあります。
そんな時は思い切って、友達とカラオケに行ったり、ランチに行ったりしました。
日頃から気分転換や楽しむ時間も必要と考えていたので、家族とテレビを観てワイワイする時間もあえて設けるようにしていました。
ただ、そうしてばかりではいけないなと思った時にはやらないよりは意味があると考え、好きな科目・得意な科目をやっていました。
やる気が戻ってきたら、苦手な科目に取り掛かるようにしていました。
合格のコツ
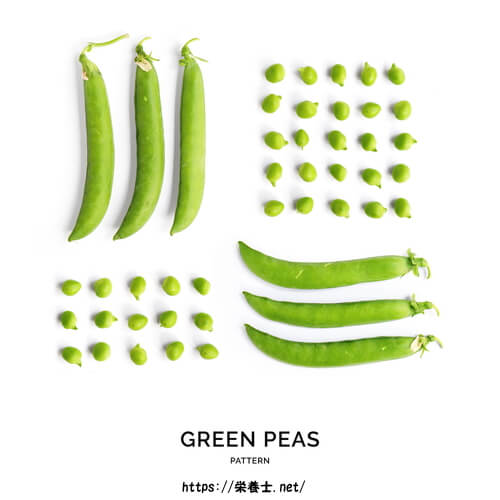
合格のコツとしては、あれこれ沢山の参考書に手を広げずに、1つの参考書をとにかくしっかり理解をするまで繰り返しやるのが良いと思います。
難しい科目も多く、覚えることも沢山あるけれど、地道に根気よくやっていけば合格は見えると思います。
前述でもお話ししたように初めは理解力も全然なく、成績も悪かったです。
けれど、上記でお話しした勉強方法を続けて、国家試験後は「多分受かったな」と手ごたえを持ったというのが正直なところです。
管理栄養士の知識は日常でもとても役立つので取得して良かったと思う資格です。
私の体験談が少しでも参考になってくれたらとても嬉しいです。ぜひ、「合格」という喜びをを手に入れてください。